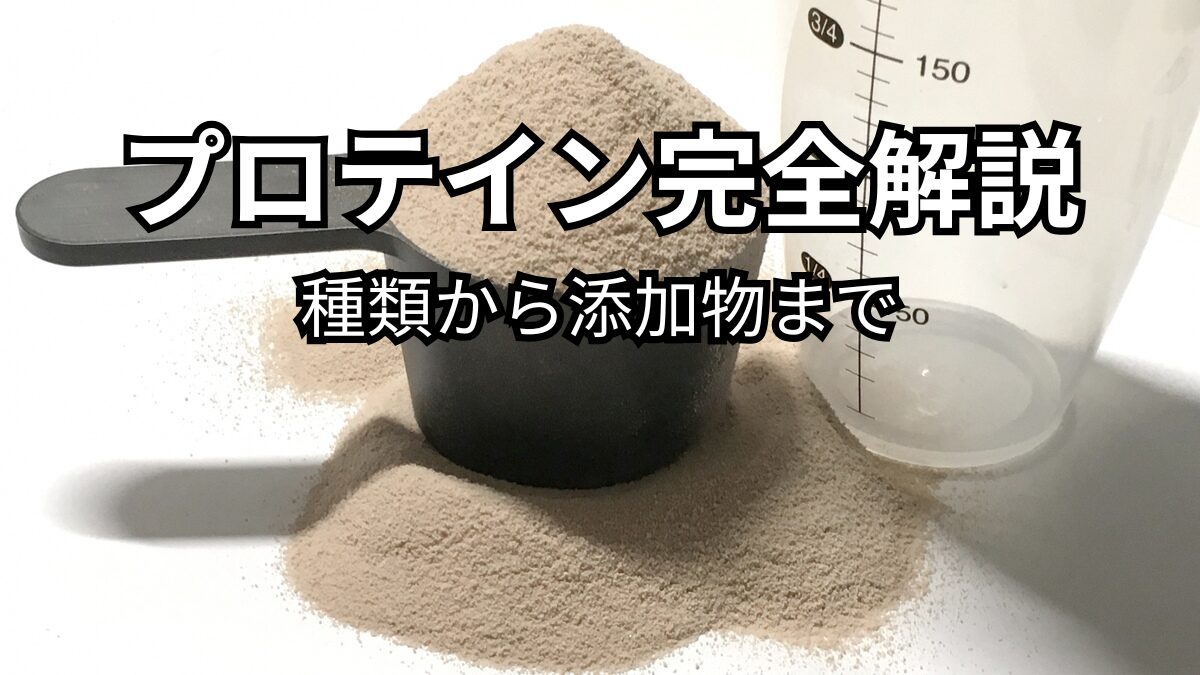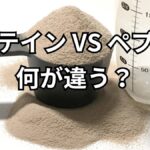「プロテイン、どれを選べばいいの?」そう思ってホエイプロテインを買ったはいいものの、次にWPC?WPI?カゼイン?ソイ?…と、たくさんの種類があって戸惑っていませんか?
「ホエイは吸収が速い」「ソイは美容にいい」という話はよく聞くけれど、実は同じ種類でも“製法の違い”で、全くの別物になることがあります。まるで、同じお米でも「玄米」と「白米」で栄養や食感が違うように、プロテインも「どう作られているか」を知ることで、自分にぴったりの商品を見つけられるようになります。
この記事では、主要なプロテインの種類(ホエイ・カゼイン・ソイ)と、その製法による違いを、身近な比喩を使いながら徹底的に解説します。製法を理解すれば、価格や味、吸収速度まで納得して選べるようになります。もうプロテイン選びで迷うことはありません。
60秒でわかるこの記事のポイント!
- ホエイプロテイン(WPC/WPI/WPH)は、「お米の精米度」に例えるとわかりやすい。
- WPC(コンセントレート)は「玄米や七分づき米」のように、栄養や脂質も少し残っていてコスパが良い。乳糖でお腹がゴロゴロしやすい人は注意が必要です。
- WPI(アイソレート)は「精米したての白米」のように、純度が高く乳糖がほぼゼロなので、お腹が弱い人や減量中におすすめです。
- WPH(加水分解物)は「おかゆ」のように、既に消化された状態なので吸収が速いですが、少し苦味があり高価です。
- カゼインプロテインは、製法で大きく性質が変わる。
- ミセルカゼインは、胃の中でゆっくり固まって溶ける「溶けないゼリー」のようなイメージ。就寝前や長時間の栄養補給に最適です。
- カゼイン塩(カゼインナトリウム、カゼインカルシウム)は、水に溶けやすい「粉ゼリーの素」のようなイメージ。すぐに溶けるので、料理やパン作りなどに向いています。
- ソイプロテインも製法で純度が変わる。
- SPC(コンセントレート)は不純物がやや残り、SPI(アイソレート)は純度が高いです。抽出方法(水かアルコールか)でも、イソフラボンの残り具合が変わってきます。
- プロテインの「溶けやすさ」は、レシチンという加工で大きく変わります。大豆やひまわり由来のレシチンで粒子をコーティングすることで、水と混ざりやすくなります。
- ピープロテインは、ホエイとほぼ同等の筋力アップ効果が期待できると研究で示されています。メチオニンが不足しがちなので、ライスプロテインなどと混ぜて使うのがおすすめです。
1.ホエイプロテインを“製法”で解像する

1-1. 原料の違い:チーズ由来 vs ネイティブホエイ
私たちが普段スーパーで見かけるホエイプロテインのほとんどは、**チーズを作る過程でできる“副産物”**として生まれる乳清(ホエイ)から作られています。これはチーズ工場のコストを抑えつつ、栄養価の高いプロテインを効率よく作る方法です。
一方で、ネイティブホエイは、生乳から直接ホエイ成分だけを分離させて作られます。これは手間がかかりますが、牛乳本来の良質なタンパク質のバランスが保たれるという特徴があります。
1-2. WPC / WPI / WPH の工程と性質
この3つは、ホエイからタンパク質をどれだけ「濾過(ろか)」したか、という製法の違いです。
WPC(コンセントレート)
「コンセントレート」は「濃縮」という意味。
ホエイからタンパク質を濃縮したものです。超ろ過膜という小さな穴のあいたフィルターで、余分な水分やミネラルなどを取り除きます。これにより、タンパク質が70〜80%にまで濃縮されます。
- 特徴: 乳糖や脂質が少し残るので、風味が豊かで、比較的安価です。
- 注意点: 乳糖が多く残るため、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする「乳糖不耐症」の人は注意が必要です。
- 比喩: 「お米の玄米」や「七分づき米」のように、栄養も少し残っているが、不純物(乳糖や脂質)も残っているというイメージです。
WPI(アイソレート)
「アイソレート」は「分離」という意味。
WPCをさらに細かくろ過して、タンパク質の純度を高めたものです。ろ過の方法には、CFM(クロスフローマイクロフィルトレーション)と呼ばれる物理的なろ過や、イオン交換法などがあります。
- 特徴: タンパク質純度が90%以上と非常に高く、乳糖や脂質はごくわずかしか残りません。そのため、乳糖不耐症の方でも安心して飲むことができます。
- 比喩: 「精米したての白米」のように、タンパク質だけを純粋に精製したイメージです。
WPH(加水分解)
「ハイドロライズド」は「加水分解」という意味。
WPCやWPIを酵素で分解し、あらかじめ消化された状態(ペプチド)にしたものです。これにより、体への吸収がさらに速くなります。
- 特徴: 吸収速度が一番速いのが最大のメリット。消化の負担も少ないので、胃腸が弱い方や、トレーニング直後の栄養補給を最優先したい方におすすめです。
- 注意点: 酵素分解の過程で、独特の苦味が出やすいのがデメリット。また、製造コストが高いため、価格も高価になります。
- 比喩: 「おかゆ」のように、お米を煮崩して(分解して)いるので、消化の必要がなく、スルスルと体に吸収されるイメージです。
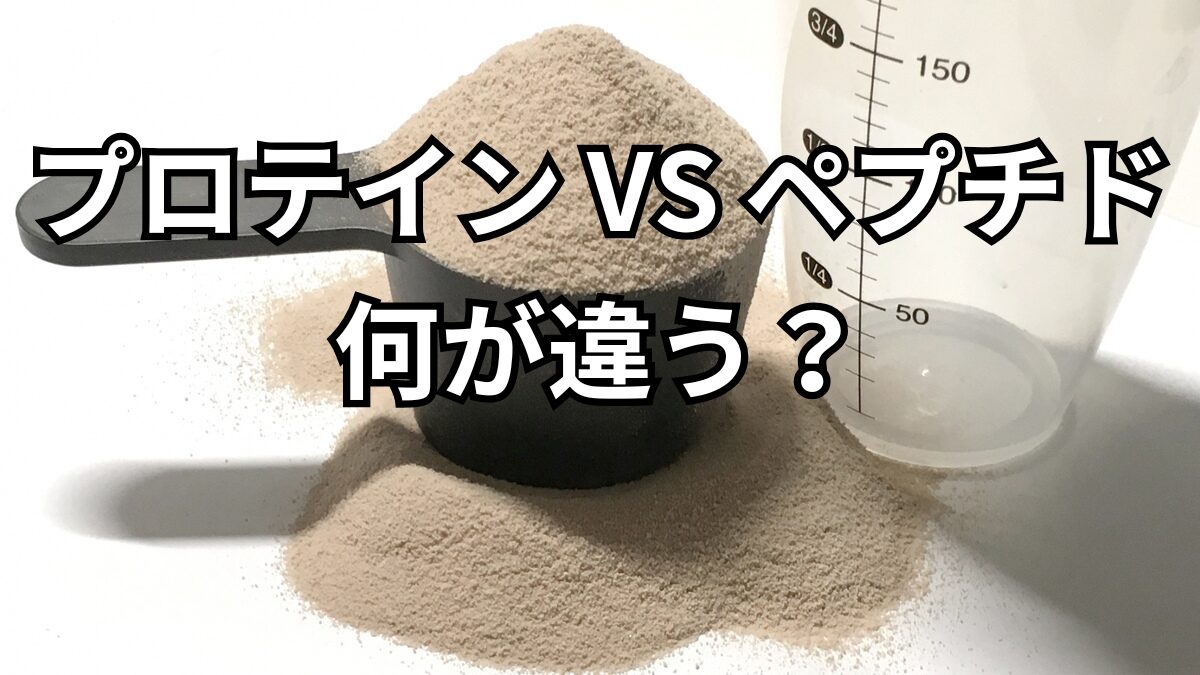
2.カゼインプロテインとは?
カゼインは、牛乳のタンパク質の約80%を占める成分です。ホエイが「水に溶けやすい」のに対し、カゼインは「水に溶けにくい」という性質を持っています。
2-1. どんな種類がある?
ミセルカゼイン
牛乳の中では、カゼインは「ミセル」という球状の構造を保っています。この構造を壊さずに抽出したのがミセルカゼインです。
- 特徴: 胃の中に入ると、ミセルが酸と反応して固まります。この「固まり」が時間をかけてゆっくりと消化されるため、最大で6~7時間もかけてアミノ酸を供給し続けることができます(※3,12)。
- 比喩: 「ゆっくり溶けるゼリー」のようなイメージ。
カゼイン塩(カゼインナトリウム、カゼインカルシウム)
牛乳からカゼインを酸で沈殿させ、ナトリウムやカルシウムを加えて溶けやすくしたものです。
- 特徴: ミセル構造が壊れているため、水に溶けやすく、サラサラしています(※3)。
- 比喩: 「水にすぐ溶ける粉ゼリーの素」のようなイメージ。
2-2. 使い分け
- 就寝前の栄養補給や、食事の間隔が空くときには、持続的にアミノ酸を供給するミセルカゼインが最適です。
- 料理やお菓子作りなど、水に溶けやすい性質を活かしたい場合は、カゼイン塩が向いています。
3.ソイプロテイン:SPC/SPIと抽出法の落とし穴
ソイプロテインは、大豆を原料とした植物性のプロテインです。
3-1. 製法の違いによるソイプロテインの選び方
ホエイと同じように、ソイも製法で純度が変わります。
- SPC(ソイプロテインコンセントレート):タンパク質が約65〜70%に濃縮されたもの。食物繊維/糖質をやや残す→風味/価格にメリット。
- SPI(ソイプロテインアイソレート):タンパク質が90%前後の高純度なもので乳糖ゼロ派・ダイエット設計に◎(※4,5)。
3-2. 抽出法で変わるイソフラボン
ソイプロテインの製造には、アルコールを使う方法と、水を使う方法があります。
- アルコール抽出: イソフラボン(大豆に含まれる女性に嬉しい成分)が減少しやすいです。大豆特有の機能性を抑えたい/風味軽減の狙い(※4)。
- 水抽出: イソフラボンが比較的多く残ります。美容/更年期サポート狙いなら相性がいい(※4,5)。
美容や健康目的でイソフラボンも摂取したい場合は、「水抽出」と書かれたSPIを選ぶのがおすすめです。
3-3. 消化と抗栄養因子
- 加熱/酵素処理でトリプシン阻害因子は大幅低減。消化率は高い(※4)。
- FODMAP感受性がある人は、ソイでも分離度の高いSPIの方がマシなことが多い。
4. ピー・ライス・ヘンプ・エッグの“製法とクセ”
4-1. ピープロテイン(Pea)
エンドウ豆を原料としたプロテイン。アレルギーを起こしにくく、ヴィーガンの方にも人気です。
特徴: アレルギーが起きにくく、ヴィーガン対応。ただし、必須アミノ酸の「メチオニン」がやや不足しがちです。
使い方: メチオニンが豊富なライスプロテインなどとブレンドすることで、アミノ酸のバランスを完璧にすることができます(※6,7)。
4-2. ライスプロテイン
玄米・白米から酵素を使って抽出したプロテインで消化に良い。
特徴: 消化が良く胃腸に優しい。ピープロテインとは逆に「リジン」が不足しがちです。
使い方: ピープロテインとブレンドすることで、お互いの弱点を補い合えます(※7,13)。
4-3. ヘンププロテイン(Hemp Protein)
麻の実を低温で油を搾り、その残り(搾りかす)を乾燥して粉にしたもの。イメージは「豆乳を絞った後のおからを粉にする」感じ。
特徴:タンパク質はやや低め(約50〜60%)で食物繊維とオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸)が豊富でありミネラルも含まれる。
使い方:水でシェイクするより、スムージーや料理・ベイクに混ぜるのがおすすめで、たんぱく質の補充として使うなら他のプロテインに少しブレンドして栄養のバランスを補うと◎
👉 「筋肉増強の主役」というより、健康志向・栄養補助向けのプロテインです。
4-4. エッグプロテイン(Egg Protein)
卵白を乾燥(スプレードライ)して粉にしたもの。要するに「白身だけをギュッと濃縮した粉」。
特徴:アミノ酸スコア満点で必須アミノ酸がバランス良く含まれる。吸収速度は中間でホエイより遅く、カゼインより速い。乳や大豆にアレルギーがある人でも安心だが価格がやや高め(※15)。
使い方:万能型で筋トレ後でも間食でもOK。乳糖不耐症・大豆アレルギーの人に特におすすめ。味にやや卵白っぽさが残るので、フレーバー付きが飲みやすい
👉 「筋肉にも健康にもバランスよく対応できるオールラウンダー」。ただしコスト面では少し贅沢な選択肢です。
5. プロテインの添加物の正体を徹底解説
プロテインの袋を見てみると、「甘味料」「香料」「レシチン」「ビタミン」などいろいろ書かれています。
「これって体に悪いんじゃ…?」と不安になる人も多いですが、実際には飲みやすさや溶けやすさのための工夫が大半です。ここでは代表的な添加物をわかりやすく解説します。
甘味料
甘味料はホエイやソイはそのままだと苦味やえぐみが強く、飲み続けにくいため、味付けに使われています。
- 種類と特徴
- スクラロース、アセスルファムK → 一般的。カロリーゼロで安定した甘さ。
- ステビア、羅漢果 → 植物由来の甘味料。やや独特な後味。
- まとめ:甘味料は“飲みやすさのための調味料”。気になる人はプレーン味を選べばOK。
香料
香料は風味付けです。プレーンのままだと乳臭さや豆臭さが気になるため、バニラ・チョコ・いちごなどで飲みやすく調整。
- 体への影響は?
食品添加物として安全性が確認されている香料が少量入っているだけ。
インスタント加工(Instantized)
- プロテインが粉のままだと水をはじいてダマになりやすいので、レシチン(大豆やヒマワリ由来の油分)でコーティングしてあります。
- これがあると水にサッと溶けやすく、シェイクもなめらかになります。
- たとえるなら「ホットココアの粉をそのまま入れるとダマになるけど、インスタントコーヒーはサッと溶ける」みたいな違いです。
インスタント加工の見分け方
1. ラベル・原材料表示で確認
- 原材料に 「大豆レシチン」 や 「ひまわりレシチン」 と書かれていれば、インスタント加工されている証拠です。
→ レシチンでコーティングするのが“インスタント化”の基本だからです。
2. 実際に溶かしてみる
- インスタント加工あり:水を入れて軽く振るだけでスッと溶ける。泡は多少出るが、すぐに落ち着く。
- インスタント加工なし:粉が水面で浮いたままダマになりやすく、底に残りがち。しっかり振ってもザラザラ感が残る。
3. 見た目での違い(粉の状態)
- インスタント加工あり:粉がサラサラしていて、やや粒が大きめでしっとり感がある。
- インスタント加工なし:きめ細かい粉で、舞いやすく、軽い感じ。
泡立ちの原因と消泡剤
- プロテインを振ると泡が立ちますが、これはたんぱく質が“泡を抱え込みやすい性質”を持っているから。
- 泡が立つのは「ちゃんと水に溶けた証拠」でもあり、必ずしも悪いことではありません。
消泡剤
- 市販の紙パックや缶の「飲むプロテイン(RTD)」では、製造過程で泡を抑えるためにごく少量のシリコーン系添加物を使うことがあります。
- でも、粉のプロテインは基本的にレシチンや配合の工夫で泡を抑えているので、特別な消泡剤はほぼ入っていません。
6. “数値で見る”比較表
| 種類 | 代表製法/キーワード | たんぱく純度目安 | 乳糖 | 吸収速度 | ロイシン/25g目安 | 味/溶け | 向く目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホエイWPC | UF/膜分離 | 70–80% | △ | 速 | 2.6–2.9g | コク/泡やや出 | コスパ増量、間食 |
| ホエイWPI | CFM/イオン交換 | 88–92% | ほぼ0 | 最速寄り | 3.0g | さっぱり/溶け◎ | 乳糖不耐・減量・就トレ |
| ホエイWPH | 酵素加水分解 | 85–90% | 0 | 最速 | 3.0g | 苦味あり/溶け◎ | 即吸収・胃腸対策 |
| ミセルカゼイン | ミセル保持膜分離 | 78–85% | △ | 遅 | 2.2g | 濃厚/とろみ | 就寝前/置換 |
| カゼイン塩 | caseinate | 85–90% | △ | 中〜遅 | 2.2g | 溶け◎ | 料理混用/万能 |
| ソイSPI | アイソレート(水orアルコール抽出) | 85–90% | 0 | 中 | 2.0g | 風味クセ | 美容/ビーガン/置換 |
| ピー | 乾式/湿式分離 | 80–85% | 0 | 中 | 2.2g | とろみ | アレルギー配慮/ブレンド |
| ライス | 酵素抽出 | 75–80% | 0 | 中 | 1.9g | 粉感あり | ブレンド補完 |
| エッグ | スプレードライ | 80–85% | 0 | 中 | 2.3g | 卵風味 | 乳糖回避/万能 |
| ※ロイシンは一般値の目安(製品差あり)(※10,11,13,15) | |||||||
まとめ
- “同じ種類でも製法が違えば実力も別物”。ホエイならWPC/WPI/WPH、カゼインならミセル vs 塩、ソイはSPI/SPCと抽出法、ピー/ライスはブレンド設計まで見る。
- 吸収速度は“場面の最適化”に使う。速さ=就トレ/朝、遅さ=就寝前。
- 乳糖耐性・味・価格の三角トレードオフを理解し、WPI(速/高/淡)×WPC(並/安/コク)の使い分けが王道。
- 溶け・泡は“処方と物性の話”。Instantizedか、レシチン源と振り方で体感が変わる。
- ビーガンやアレルギーでも、ピー×ライスで**アミノ酸の谷(リジン/メチオニン)**を埋められる。
- 最終的には、体質(胃腸・乳糖)×味の許容×目的(増量/減量/美容)×タイミングで“あなたの最適”を組むのがベスト。
参考文献
※1:Smithers GW. Whey and whey proteins—From “gutter-to-gold”. Int Dairy J. 2008.
※2:Korhonen H. Milk-derived bioactive peptides: Processing and release. Int Dairy J. 2009.
※3:Boirie Y, et al. Slow and fast dietary proteins… PNAS. 1997.
※4:Riaz MN. Soy Applications in Food. CRC Press, 2006.
※5:Messina M. Soy isoflavones and health. Am J Clin Nutr. 2014.
※6:Babault N, et al. Pea protein vs whey for hypertrophy. JISSN. 2015.
※7:Gorissen SH, et al. Protein quality/DIAAS across sources. Nutrients. 2018.
※8:食品添加物公定書/飲料製造における消泡剤の一般的使用範囲(総説)。
※9:Walstra P, et al. Dairy Science and Technology. CRC Press, 2006.
※10:Phillips SM. Protein and muscle hypertrophy. J Sports Sci. 2014.
※11:Tang JE, et al. Fast vs slow proteins and MPS. J Physiol. 2009.
※12:Res PT, et al. Casein before sleep augments MPS overnight. Med Sci Sports Exerc. 2012.
※13:Joy JM, et al. Rice protein vs whey post-exercise. Nutrition Journal. 2013.
※14:House JD, et al. Nutritional value of hempseed. J Agric Food Chem. 2010.
※15:Velázquez-Vidal D, et al. Egg white proteins: Tech/functional properties. Foods. 2022.
免責事項
本記事は研究知見に基づく一般情報で、特定製品の効果を保証するものではありません。持病・薬の併用・食物アレルギーがある方は、使用前に医師や管理栄養士へご相談ください。