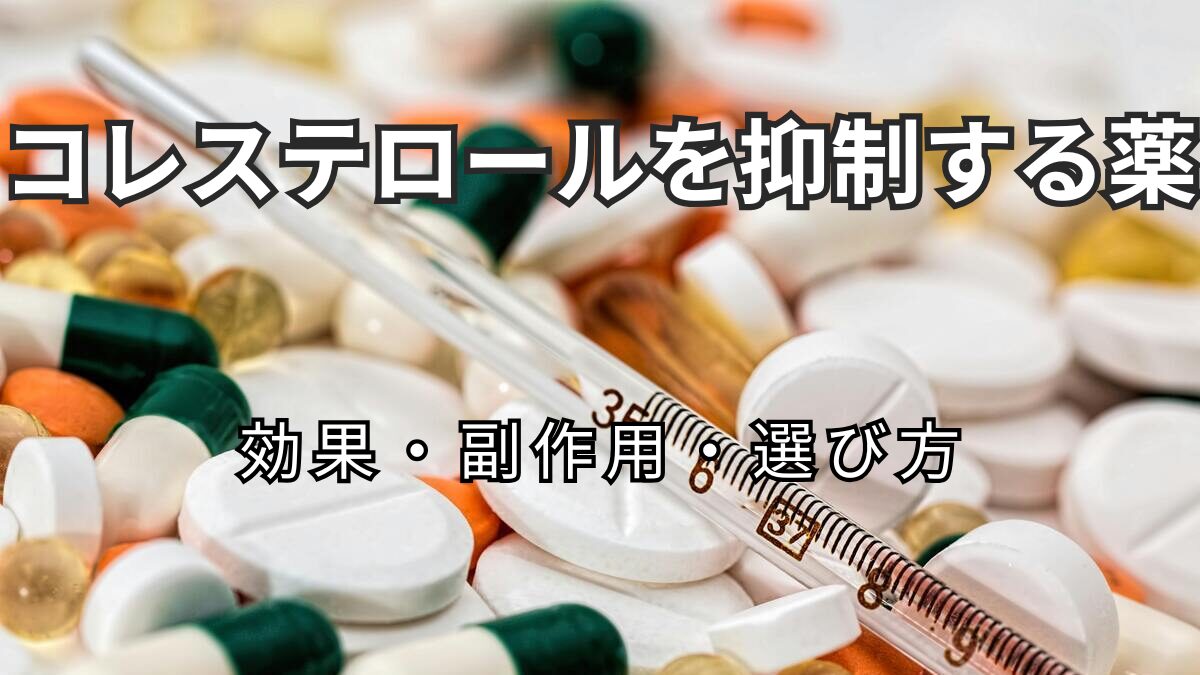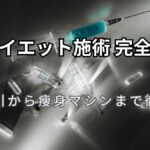肥満とともに気になるのが「生活習慣病リスク」。
特に 高コレステロール血症(脂質異常症) は、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞の原因となります。
このリスクを減らすために使われるのが コレステロールを抑制する薬 です。
直接的に体重を落とす薬ではありませんが、肥満に伴う合併症を防ぎ、長期的に健康な体を維持するための重要な治療薬です。
この記事では、コレステロールを下げる代表的な薬の種類と仕組み、副作用、そしてダイエットとの関わりについて解説します。
60秒でわかる!この記事のポイント
- 主な薬の種類:スタチン系、エゼチミブ、フィブラート系、PCSK9阻害薬
- 作用機序:肝臓でのコレステロール合成抑制、吸収抑制、排出促進など
- 効果:LDLコレステロールを低下させ、動脈硬化や心血管疾患のリスクを減らす
- 副作用:肝機能障害、筋肉痛、消化器症状など(薬の種類による)
- まとめ:肥満治療そのものではないが、生活習慣病リスクを下げるためには重要な治療選択肢
コレステロールを抑制する薬の種類と特徴
1. スタチン系(アトルバスタチン、ロスバスタチンなど)
- 仕組み:肝臓でのコレステロール合成を抑える
- 効果:LDLコレステロールを20〜50%低下(※1)
- 副作用:肝機能障害、筋肉痛・横紋筋融解症(まれ)
- 👉 スタチン系は高コレステロール血症の第一選択薬とされ、日本動脈硬化学会のガイドラインでも推奨されています(※1)
2. エゼチミブ
- 仕組み:小腸でのコレステロール吸収を抑える
- 効果:LDLコレステロールを15〜20%低下
- 副作用:下痢、肝機能障害
- 👉 スタチンが使えない人や、スタチンと併用するケースで有効(※2)
3. フィブラート系(フェノフィブラート、ベザフィブラートなど)
- 仕組み:中性脂肪を下げ、HDLコレステロールを増やす
- 効果:高トリグリセリド血症に有効
- 副作用:肝機能障害、胆石リスク
- 👉 「中性脂肪が高い人」に処方される
4. PCSK9阻害薬(エボロクマブ、アリロクマブ)
- 仕組み:LDL受容体の働きを強化し、血中LDLを減らす
- 効果:強力にコレステロールを下げる(50〜60%低下)(※2)
- 副作用:注射部位反応、インフルエンザ様症状
- 👉 家族性高コレステロール血症や、薬で十分に下がらない場合に使用
ダイエットとの関わり
- コレステロールを下げる薬自体は「体重減少薬」ではない
- ただし、肥満と脂質異常症はセットで起こりやすいため、ダイエット治療と並行して用いられることが多い
- 食事・運動と併用することで、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な合併症を防ぐ効果が期待される
副作用と注意点
- スタチン系:筋肉痛・肝機能障害
- フィブラート系:胆石リスク
- PCSK9阻害薬:注射が必要で高額
👉 自己判断で服用する薬ではなく、血液検査に基づいて医師が適切に処方する薬。
詳しいまとめ
コレステロールを抑制する薬は、肥満治療薬とは違い「体重を減らす」ことが目的ではありません。
しかし、スタチン系やエゼチミブ、フィブラート系、PCSK9阻害薬などは、LDLコレステロールや中性脂肪を下げることで、動脈硬化や心筋梗塞・脳梗塞といった生活習慣病のリスクを大幅に減らします。
肥満や糖尿病と重なりやすい脂質異常症に対しては、生活習慣の改善と並行して薬を使用することが、長期的な健康維持に欠かせません。
つまり「痩せる薬」ではなく「合併症を防ぐ薬」としての位置づけですが、ダイエットとの相乗効果で大きな意味を持ちます。
参考文献
※1:日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022」
※2:Stone NJ, et al. “2018 AHA/ACC Guideline on the Management of Blood Cholesterol.” J Am Coll Cardiol. 2019.
※3:厚生労働省 医薬品医療機器総合機構(PMDA) 添付文書検索
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の薬の使用を推奨するものではありません。
薬の使用にあたっては必ず医師の診断を受け、指導に従ってください。
生活習慣病の治療は、薬だけでなく食事・運動の改善と並行して行うことが重要です。