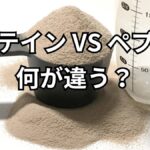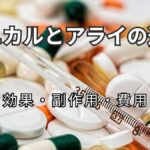減量を続けていると、どうしても訪れる“停滞期”。
「一度思いきり食べた方がいい」「カロリーを上げると代謝が戻る」と聞いたことがある人も多いでしょう。
その時に出てくるのが、リフィード(Refeed) と チートデイ(Cheat Day)。
どちらも「食べることで代謝を回復させる」という発想ですが、
実は似ているようで、目的もメカニズムもまったく別物です。
しかも、近年の研究では「チートデイが必ずしも有効ではない」「リフィードも一部の条件でしか代謝を戻さない」との報告も。
本記事では、
👉 両者の科学的な違い
👉 本当に代謝は上がるのか?
👉 どう使い分ければいいのか?
を、最新のエビデンスをもとにわかりやすく解説します。
60秒でわかるこの記事のポイント!
- 「リフィード=計画的な糖質リカバリー」「チートデイ=感情的な暴食デイ」
- リフィードの目的はレプチン(食欲・代謝ホルモン)を一時的に回復させること
- チートデイは心理的リセット効果が主。代謝への影響は限定的
- 最新研究では「2日間の高炭水化物リフィード」は脂肪減少を妨げず代謝を維持(※1)
- 「好きに食べてOK」は誤解。どちらも“戦略的に使う日”でなければ意味がない
リフィードとチートデイの違い
| 比較項目 | リフィード(Refeed) | チートデイ(Cheat Day) |
|---|---|---|
| 目的 | ホルモン・代謝の一時回復 | 精神的リフレッシュ、食欲解放 |
| 方法 | 高炭水化物中心・カロリー計算あり | 制限なし(好きなだけ食べる) |
| 頻度 | 週1〜2回(または2日連続) | 不定期・気分次第 |
| 主な栄養源 | 炭水化物多め・低脂質 | 高脂質・高糖質・高塩分になりがち |
| 効果 | レプチン・グリコーゲン補充、代謝維持 | 心理的満足感、一時的なNEAT上昇 |
| デメリット | 効果は短期的・条件付き | 食欲暴走・脂肪再蓄積リスク |
リフィード:代謝を「一時的に再点火」する科学
リフィードの狙いは、長期的なカロリー制限で下がった代謝を一時的に回復させること。
その鍵となるのが、**レプチン(leptin)**というホルモンです。
カロリー不足が続くと、体脂肪量の減少に比例してレプチンも減少。
その結果、
- 食欲が増す
- 代謝が落ちる
- 活動量が減る
という“省エネモード”になります(※2)。
リフィードで一時的に糖質を多く摂取すると、
血糖とインスリンの上昇によってレプチン分泌が促進され、
代謝・熱産生が短時間で回復する可能性があると報告されています(※3)。
💡 ただし、これは「数日間続くほどの劇的効果」ではなく、1〜2日程度で消える一時的反応。
つまり、リフィードは「停滞期をリセットするスイッチ」であり、「代謝を永続的に上げる魔法」ではありません。
チートデイ:「好きなだけ食べる日」の誤解
一方のチートデイは、心理的なリセットを目的とするもの。
ダイエット中のストレスを和らげ、過度な制限による反動を防ぐ効果が期待されます。
しかし、問題は“やり方”。
脂質と糖質を同時に大量摂取すると、インスリンが急上昇し、余剰エネルギーがそのまま脂肪に変わります。
また、一度の暴食で体重が1〜2kg増えるケースも珍しくありません(ほとんどは水分ですが)。
⚠️ 「チートデイをすれば代謝が上がる」というのは誤解。
実際の研究では、短期的にエネルギー消費が上がるのは数時間だけで、
総合的には「ただカロリーが増えるだけ」のことが多いのです(※4)。
最新研究が示す結論:代謝回復は“限定的”
- Campbell et al., 2020(※1)
→ 7週間のダイエット中、2日間の高炭水化物リフィードを設けた群は、連続制限群と比較して筋肉量の減少が少なく、代謝維持率が高かった。 - Dirlewanger et al., 2000(※3)
→ 炭水化物リフィードによりレプチン分泌が一時的に上昇(24〜48時間)。 - Brown et al., 2022(※4)
→ チートデイ群では食後代謝の一時上昇は見られたが、体脂肪率はむしろ微増傾向。
つまり、「リフィードは条件付きで有効」「チートデイは気晴らし程度に留めるのが現実的」というのが現在の科学的結論です。
実践アドバイス:「リフィードするか?チートするか?」
| 状況 | 選ぶべき戦略 | 理由 |
|---|---|---|
| 長期のカロリー制限で停滞中 | リフィード | グリコーゲン・レプチンを一時回復し、代謝を維持 |
| ストレスが強くモチベが限界 | 軽いチート | 精神的リセット目的で一食だけ“自由”に |
| 週末に暴飲暴食を繰り返している | どちらも不要 | リフィードではなく「カロリーリバランス」を整える段階 |
🎯 「自由に食べる日」ではなく「戦略的に食べる日」。
体をリセットするか、心をリセットするか──目的を明確に使い分けましょう。
まとめ:リフィードもチートも“戦略的に”使えば武器になる
- リフィード:ホルモン・代謝を一時的に整える“再点火デー”
- チートデイ:心理的ストレスを和らげる“ガス抜きデー”
- どちらも万能ではなく、使い方を間違えると脂肪を戻す
- 最も大事なのは「1日のリセット」ではなく、「長期の一貫性」
- 減量期こそ“食べない戦略”より、“どう食べて回復するか”が差をつける
🍚 ダイエットは「我慢」ではなく「調整」。
科学を使って“食べるタイミング”を味方につけよう。
その他の食事法についての科学的研究はこちら

参考文献
※1 Campbell BI, et al. J Strength Cond Res. 2020;34(9):2563–2572.
※2 Rosenbaum M, et al. Am J Clin Nutr. 2008;88(3):678–684.
※3 Dirlewanger M, et al. Am J Clin Nutr. 2000;71(2):332–338.
※4 Brown C, et al. Nutrients. 2022;14(6):1189.
免責事項
本記事は科学的文献に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
個人の体質・健康状態・活動量によって最適な摂取方法・頻度は異なります。
チートデイ・リフィード導入を行う際は、医師・栄養士・トレーナーなどの専門家にご相談ください。